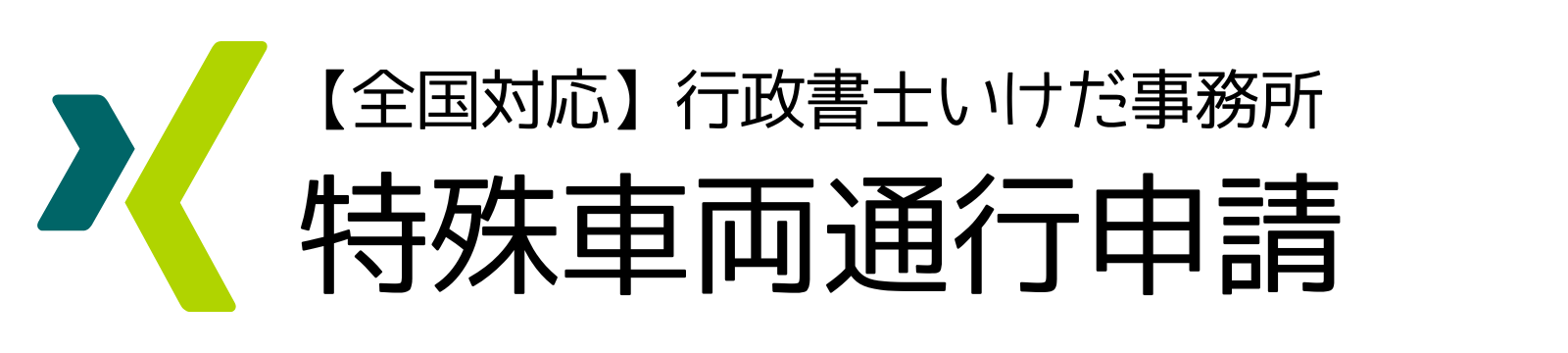自社のトラックが、特殊車両通行申請手続きの申請対象になるのかどうか。その判断基準を正確に知りたい、と考えている方も多いのではないでしょうか。
特殊車両に関するルールは複雑で、どこから調べればいいのか分かりにくいと感じることもあるかもしれません。
この記事では、特殊車両の定義と、その基準となる「一般的制限値」について、専門用語を避けながら要点を絞って解説します。
この記事を読み終える頃には「何が基準で、何に注意すべきか」がスッキリと明確になっていると思います。
ぜひこの記事をお役立てください。
「特殊車両」とは?
新車をたくさん積んだ自動車運搬用のトレーラや液体を運ぶための大きなタンクをもったトレーラ。街でそういった車両を見かけて、「あんなに長くて大きい車、普通の道路を走っても大丈夫なのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?
結論から言うと、そういった車は「特殊車両」と呼ばれ、自由に公道を走ることはできません。
特殊車両とは、ひとことで言えば「法律で決められたサイズや重さの基準を、ひとつでも超えてしまう車」のことです。
では、なぜこのような基準があるのでしょうか。
もし、どんなに大きくて重い車でも自由に道路を走れるとしたら、道路のアスファルトを傷つけたり、橋が重さに耐えきれずに壊れたり、狭いカーブを曲がりきれずに対向車とぶつかったりと重大な事故につながる危険があるからです。
こうした事態を防ぎ、皆が使う大切な道路や橋を守るために、法律で「公道を走る車は、このサイズ・重さまでにしてください」という共通のルールが定められています。
この基準のことを「一般的制限値」と呼びます。
そして、仕事の都合上、どうしてもこの基準を超えてしまう車両(=特殊車両)を走らせる場合には、事前に「この車両をこのルートで通行させたいです。」という許可申請をする必要があります。
これが基準!「一般的制限値」の具体的な数値
特殊車両かどうかは「一般的制限値」という基準を超えるかどうかで決まる、とご説明しました。
では、その「一般的制限値」とは、具体的にどのような数値なのでしょうか。
ここでは、重要となる「寸法」と「重量」、そして「運動性能」に関する基準を一覧表でご紹介します。
ご自身の車両がどれか一つでもこの数値を超えていないか、チェックしてみてください。
| 寸法 | 一般的制限値 | 備考(かんたんな説明) |
| 幅 | 2.5 m | 車両の横幅です。 |
| 長さ | 12.0 m | 車両の長さです。 |
| 高さ | 3.8 m | 地面から車両の一番高い部分までの高さです。 |
| 重量 | 一般的制限値 | 備考(かんたんな説明) |
| 総重量 | 20.0 t | 車両本体、人、そして荷物も全部含んだ全体の重さです。 |
| 軸重 | 10.0 t | 1つの車軸(左右のタイヤをつなぐ軸)にかかる重さです。 |
| 輪荷重 | 5.0 t | 1つのタイヤにかかる重さです。 |
| 隣接軸重 | 18.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満) 19.0t(隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下) 20.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上) | 隣り合った2つの車軸にかかる重さの合計です。車軸間の距離によって上限値が変わります。 |
| 運動性能 | 一般的制限値 | 備考(かんたんな説明) |
| 最小回転半径 | 12.0 m | ハンドルをいっぱいに切って回った時に、一番外側のタイヤが描く円の半径です。 |
【最重要ポイント】一般的制限値は「荷物を積んだ状態」で判断します!
ここで、一つ非常に大切な注意点があります。
それは、上記の数値は、トラックが空っぽの状態(空車時)ではなく、実際に荷物を積んで公道を走る状態(積載時)で判断されるということです。
例えば、トラック単体の車検証(自動車検査証)の記載では基準内に収まっていても、重い建設機械や資材を積んだことで総重量が20.0tを超えてしまった場合、その時点であなたの車両は「特殊車両」となり、許可なく公道を走ることはできなくなります。
「空の時は大丈夫だったから…」という思い込みが、意図せぬ違反に繋がるケースもあるため、必ず「荷物を積んだ時の重さ・寸法」で考えるようにしてください。
知っておくべき「特例」と「例外」
先ほどご紹介した「一般的制限値」が、特殊車両に該当するかどうかの基本的なルールとなります。
しかし、全ての道路でこのルールが画一的に適用されるわけではありません。
実は、道路の状況などに応じた「特例」や、車両の種類による「例外」が存在します。
これを知らないと、「本当は許可なく通れるのに、遠回りしてしまった…」といった非効率な運行になったり、逆に「大丈夫だと思っていたら、うっかり違反になっていた…」という事態に陥ったりすることもあります。
ここでしっかり確認しておきましょう。
特例① 高さの基準が緩和される「高さ指定道路」
高さの制限は原則3.8mですが、安全性が高いと認められた一部の道路では、基準が4.1mまで緩和されます。
このような道路を「高さ指定道路」と呼びます。
例えば、港の近くなどで背の高い海上コンテナを運ぶトレーラーがスムーズに走行できるよう活用されています。
特例② 重さの基準が緩和される「重さ指定道路」
総重量も原則は20.0tですが、高速自動車国道や構造が頑丈に作られている主要な国道などでは、車両の長さおよび軸重に応じて最大25.0tまで許可なく通行できます。
このような道路を「重さ指定道路」と呼びます。
ただし、これらの指定道路を走行している間は特例が適用されますが、指定道路から一歩でも外れて一般道へ入る場合は、元の厳しい基準(高さ3.8m、総重量20.0t)に戻るため、注意が必要です。
例外:そもそも基準が違う「新規格車」とは?
最近、「新規格車」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
この新規格車は、「高速自動車国道」および「重さ指定道路」を走行している間に限り、総重量が最大25.0t(連結車の場合は最大26.0t)までなら許可は必要ありません。
しかし、新規格車であっても、指定道路から外れて一般道(原則20.0tまでの道路)に入る場合、その時点で総重量が20.0tを超えていれば、その区間については特殊車両として許可が必要になります。
「自分のトラックは新規格車だから、どこでも許可なしで大丈夫!」というわけでは決してない、ということをぜひ覚えておいてください。
もう一歩踏み込む!知っておきたい関連ルール
特殊車両の基準を理解した上で、さらに知っておくと役立つ関連ルールが2つあります。
これらはよく混同されたり、見落とされたりしがちなポイントですので、ぜひ頭の片隅に入れておいてください。
① 「荷物が大きくはみ出す」場合には警察の許可も必要?
もし積んでいる荷物が車体の前後左右にはみ出す場合には、特殊車両の通行許可以外に「制限外積載許可」という全く別の許可が必要になることがあります。
この許可は、出発地を管轄する警察署に対して申請するものです。
この2つの許可は混同しやすいですが、管轄も手続きも違いますのでご注意ください。
② 許可が出ても「自由に走れる」わけではない?(通行条件)
無事に特殊車両通行許可が取れても、いつでもどこでも自由に走れるわけではありません。
安全を確保するために、道路管理者から「夜21時~朝6時の間に通行してください(夜間通行)」 「安全のため誘導車を前後に配置してください(誘導車の配置)」 といった、特定の「通行条件」が付されることがあります。
特に近年、誘導車の運転者には専門の講習受講が義務付けられるなど、ルールは年々厳格になっています。
こうした条件が付くことも想定して、運行計画を立てることが大切です。
基準を超えたら、次のステップへ
ここまで、特殊車両の基準となる「一般的制限値」と、その特例・例外について解説してきました。
・特殊車両とは、寸法や重量などの「一般的制限値」をひとつでも超える車両のこと。
・一般的制限値は、「荷物を積んだ状態」で寸法や重さの判断を行うのが鉄則。
・「指定道路」や「新規格車」といった、知っておくと運行に役立つ特例や例外がある。
これらのポイントを踏まえ、まずはご自身の車両が公道を走る際に、特殊車両に該当するかどうかを改めて確認してみてください。
そして、もしご自身の車両が一般的制限値をひとつでも超えてしまっている場合、そのままでは法律違反となり公道を走ることはできません。
許可なく通行した場合には、法律に基づき数十万円の罰金が科されるなど、厳しい罰則も定められています。
安全に、そして合法的に公道を走行するためには、国や自治体へ事前に申請を行い、「特殊車両通行許可」や「特殊車両通行確認」といった手続きを済ませる必要があります。
「『許可』と『確認』って何が違うの?」「手続きはどうやって進めればいいの?」
そのようなことでお困りの際は、お悩みを解決する第一歩として、まずは一度お気軽にご相談ください。