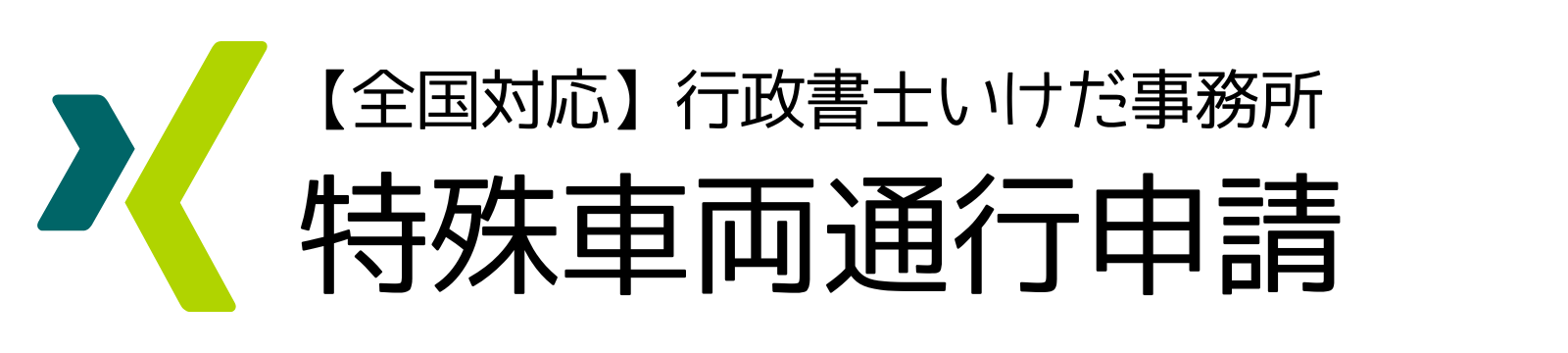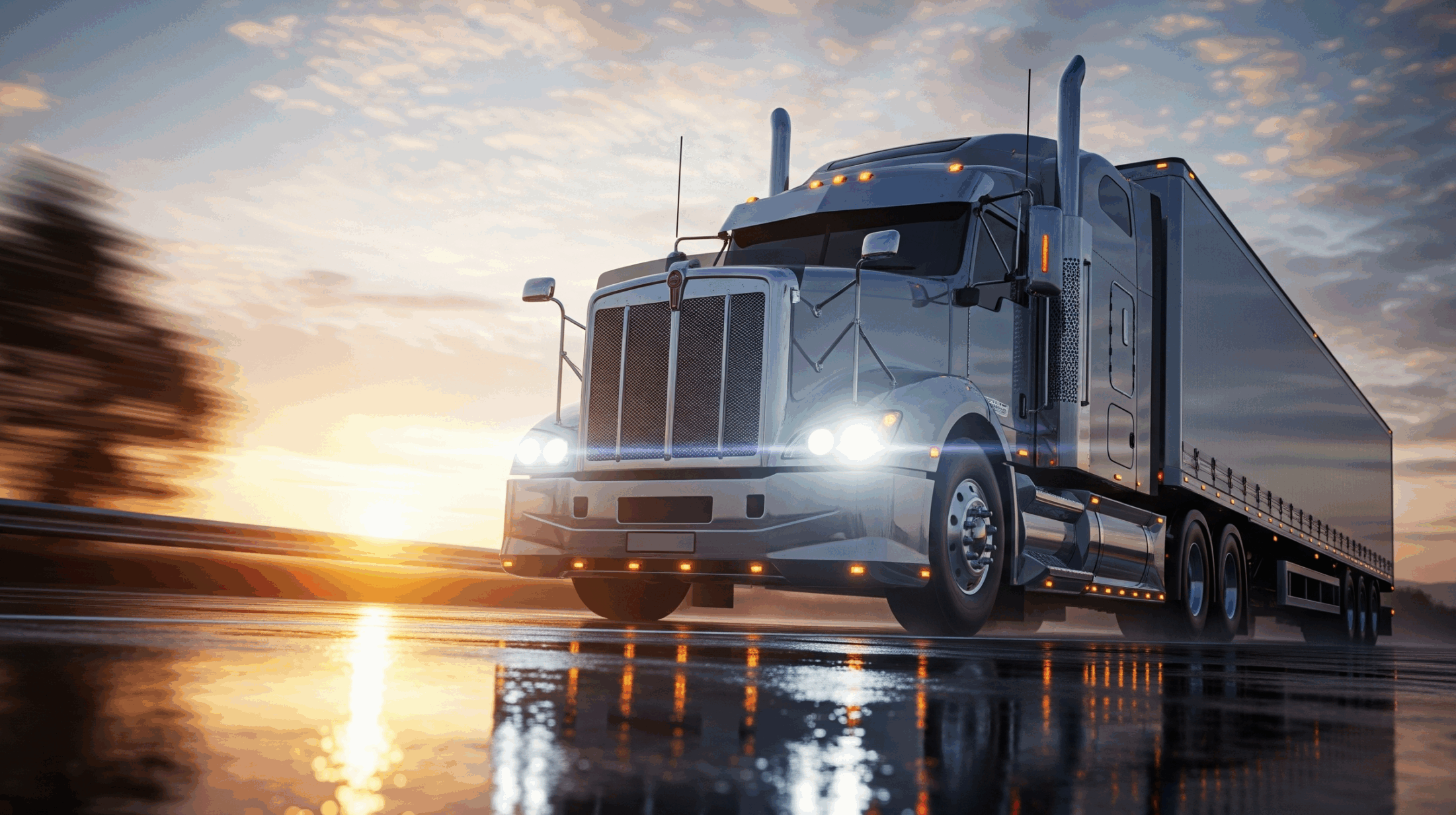特殊車両通行許可について調べていると、『C条件』や『D条件』といった見慣れない言葉が出てきて、何が違うのか分からずにお困りなのではないでしょうか。
「通行したい経路に何か条件が付くみたいだけど、一体どんな内容なんだろう…」
通行条件とは要するに「安全に通行するために設けられた追加ルール」のことです。
この条件次第で、夜間しか走行できなくなったり、誘導車が必要になったりと、業務の自由度が大きく変わるため、事前にご理解いただくことが非常に重要となります。
この記事では、そんな特車申請における通行条件について、それぞれの特徴を説明しております。
ぜひ最後までご覧ください。
「重量」と「寸法」で通行条件が異なります
通行条件とは、「この車両がこの道路を通るのは、本来は危険なので難しいのですが、特別に許可いたします。その代わり、安全のためにいくつかのルールを守ってください」という条件のことです。
そして、この条件には大きく分けて2つの種類がございます。
①重量に関する条件
車両の「重さ」が原因で、古い橋などを渡る際に付与される条件です。
②寸法に関する条件
車両の「大きさ(幅や長さ)」が原因で、狭い道や小さい交差点、見通しの悪いカーブで付与される条件です。
次の章でそれぞれ詳しく見てまいります。
【重量編】重さに関する通行条件(A条件~D条件)
こちらは、大型で重い車両が、橋のようなデリケートな場所を安全に渡るためのルールです。
AからDに進むにつれて、条件はより厳格なものとなります。
A条件:特別な条件を付さない
最も良い条件です。特別なルールは何も付かず、自由に通行いただけます。
B条件:「徐行」が求められます
B条件が付与された橋梁等を通行する際は、徐行が必要となります。
C条件:「徐行+連行禁止+後方誘導車」が必要になります
ここから条件は一気に厳しくなります。いわば「特別警備体制」が敷かれるイメージです。
C条件が付与された橋梁等では、以下の3点が求められます。
・徐行すること
・連行禁止(橋の同じ区間(径間)には、他の車両がいない状態、つまりご自身の車両1台だけで通行すること)
・上記を確実に行うため、後方に誘導車を1台配置すること
D条件:C条件に、さらに厳しいルールが加わります
こちらは現行制度で最も厳格な条件で、最高レベルの警戒態勢とお考えください。
内容は、上記のC条件の全てに加えて、さらに以下のルールが加わります。
・隣の車線を走る車にも最大限配慮し、可能な限り橋の同じ区間に他の車がいない状態を作る必要があります。(もし、すれ違い等で他の車が入ってきた場合は、一時停止すること)
【寸法編】大きさ(幅・長さ等)に関する通行条件(A条件~C条件)
こちらは、車体が大きい車両が、狭い道や小さい交差点、見通しの悪いカーブを安全に通行するためのルールです。
A条件:こちらも特別な条件はなし
重量編と同じく、特別なルールは付与されません。
B条件:狭い場所やカーブでの「徐行」義務
B条件が付与された交差点等を通行する際は、安全のために徐行することが求められます。
C条件:「徐行+前方誘導車」が必須に
寸法が原因でC条件が付く場合も「誘導車」が必要となります。
ただし、重量C条件と違うのは、対向車などとの接触を未然に防ぐため「前方」に1台配置するという点です。
・カーブや狭い道の場合: 誘導車が先の安全を確認し、その連絡や合図を受けて徐行しながら通行することが求められます。
・交差点を右左折する場合: 誘導車が先の安全を確認し、その連絡や合図を受けて、誘導車に続いて徐行しながら右左折することが求められます。
※なお、寸法に関する条件にはD条件の設定はございません。
【時間帯編】「夜間通行」になるのは、どのような車両でしょうか?
では、よく耳にする「夜間通行(原則21時~翌6時)」の制限は、どのような場合に適用されるのでしょうか。 これは、主に以下の2つのケースです。
・重量に関する条件が「D条件」と判定された車両
・寸法(幅)が「C条件」と判定され、かつ車両の幅が3mを超える車両
これらの非常に重い、または幅の広い車両は、他の交通への影響が少ない夜間に通行してください、というルールが適用されます。
【まとめ】自社の通行条件を予測し、最適な運行計画を
いかがでしたでしょうか。特殊車両通行許可の「通行条件」について、ご理解いただけたかと存じます。
通行条件は「重量」と「寸法」でルールが分かれており、厳格さが異なります。
A→B→C→Dと進むにつれ、徐行、誘導車、夜間通行など厳しい条件が付きます。
どの条件が付くかは、車両と走行する経路の組み合わせで決まります。
「許可は取れたが、厳しい条件が付いて計画通りに運べない…」 「誘導車の手配コストが、想定以上に経営を圧迫している…」
このような事態を避けるためには、許可申請の段階で、ご自身の車両がどの条件に判定されているかをしっかり確認し、場合によっては経路を変更する必要があります。
もし、ご自身の運行計画に少しでもご不安のある方、申請業務を効率化したい経営者様は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
行政書士いけだ事務所では、御社の運行計画に最適な申請方法のご提案から、複雑な申請業務の代行、そしてその後の管理まで、ワンストップでサポートいたします。
お悩みを解決する第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。